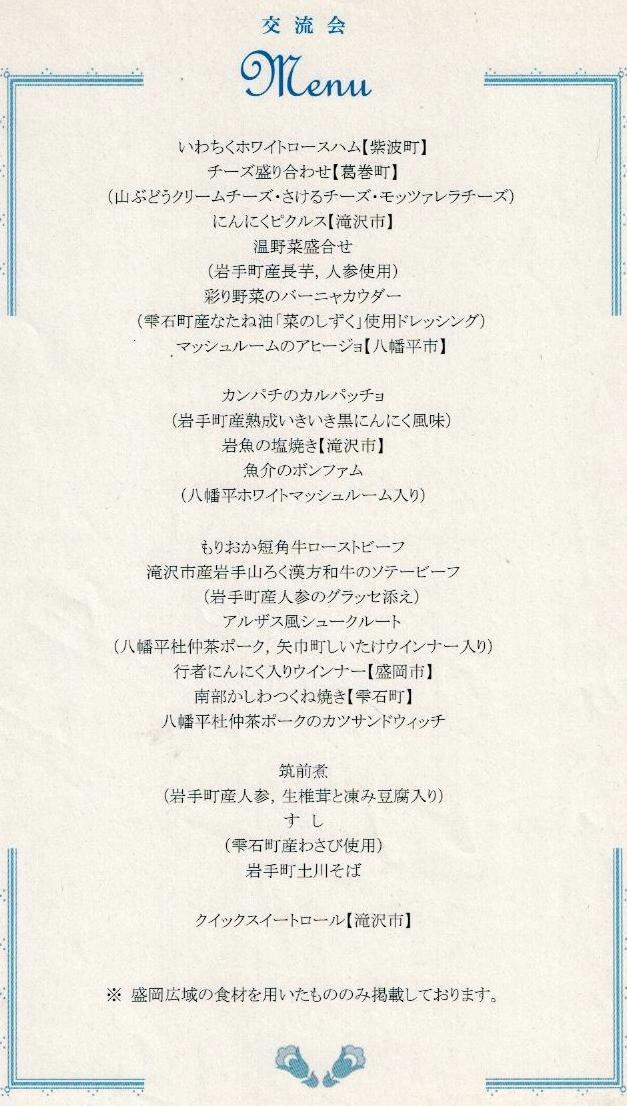�����L���Ɨ��n�Z�~�i�[2017�|2018
![]()
![]()
| �|�|�|�|�@�L�挗�Ŏ��g�ނׂ��n���n���@�|�|�|�|�@
�@��茧�̒����Ɉʒu���鐷���L��n��́A���k�V�����Ⓦ�k�����ԓ��Ȃǂ̍�����ʖԂ��������琮������A���̒n���I�D�ʐ������k���k�̋��_�Ƃ��ēs�s�@�\�W�����ĎQ��܂����B
|
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
�v���[���e�[�V���� �J���T�������s���i�����L��n��Y�Ɗ��������c���j���v���[�� �w�����L��n��̓��F�ƒn��Y�Ƃ̐U���ɂ��āx �P�D���E�����L��̊�Ɨ��n���ɂ��� �Q�D���E�����L��n��̐l�ނɂ��� �R�D�����L��n��̎Y�Ɗ������ւ̎��g�� �J���t���Ȏʐ^�Ƌ��ɂW�s���̓��F����Ղ��Љ�������܂��� |
 �܂��ŏ��ɒJ���T�������s���̈��A�A�����Ċe�s���̎����A ������F�J �g�����A���V�����蒬�������A���A���鍂��������В����Ƃ��̌��ɉB��Ȃ���w�̍����ŕ������؏d�j���������A �[�J�������Β����A�����T�G���s���A�c�����F�������s���A�J���T�������s�� |
| ���� �F �n��͂ƒn��o�ύĐ��̔��i�`�L�����ƋP�������L�挗�`�j �u�t�F�����{������������Ȍ������@���J �_���@���@�@�@ |
|
| ���J����͎R�������R�̐��܂�ŁA���R���Z�`����@�w�����A1988�N���{�J����s�i�������{����������s�j�ɓ��ЁA1992�N�R�����r�A��w�o�c��w�@�ɔh�����w����1994�N�l�a�`�����A�i���j���{�o�ό����������ǂɔh���o���Ō������ƂȂ�܂����B2007�N���{����������s�n��U�����Q�����A2012�N���{������������������Ȍ������ƂȂ�܂����B�o���͗��h�ł����A���̐l�̓����͓s�s�̋N������j�A�����Ɋւ��ċ����������āA������ɂ͎ȖڂɊW�Ȃ��u�n���v�̓Ɗw�ɗ��ł����Ƃ����_�ł��B�����͂قƂ�ǂ�����őS���𗷂��āA�J�ʂ��Ă�����{�̓S�O���iJR�E���S�E���c��ʁj�S�������悵���Ƃ����قǂł��B���������O�̑S��3,200�s�������ׂāA�C�O90����������ŕ����܂����B���̌��ʁA�n��������ڂ����c��������ŁA���̓s�s�̕�������_����͂��A����̎�����Љ�Ȃ��炻�̓s�s�̒��S�s�X�n�������Ȃǂ܂��Â���̂��������銈�����]������A�S���e�n�ŔN��400��ȏ�̍u��������Ȃ��Ƃ����X�[�p�[�}���U��ł��B���{�W�̗l�X�Ȉψ������߂Ă��܂��B����ɑł��Ă��̕��ł��� |  �u�t�F���J �_�� �� �R�������܂�53�� |
| �u�����āE�E�E�E�V������̊��z �@���J�_��́A���������đ������������Ƃ̂��ƁA�X�e�b�L�����Ă̒ɁX�����o�d�ł����B �@�u�C���[�W�ɂƂ���ĕ������l���Ă͂����Ȃ��A���Ԃ��f�[�^����c�����Ĕ��f���邱�ƁA�����̖ڂŌ��ĔF�����邱�Ɓv�̑����b����܂����B�旧���đ��J���e���r�ԑg�Łu�A�x�m�~�N�X�Ōٗp���������ƌ�������ǁA���ۂ͐l�������œ����肪�����Ă���A���ɒc��̐��オ��N���}�����Ƃ��ɂ�����[�����҂���ΓI�ɕs���A������h���h�������Ă���A����Ɍ������Ċ�Ɗ������k�����čs���Ƃ������A���������킯�ɂ͍s���Ȃ������Ƃ͍̗p�����������ɂ���A�����⍂��҂��܂߂ē��������A����ǐl����z���}�ɂ͑��₹�Ȃ�����K��p�[�g�A�A���o�C�g��������A���R���Ɨ��͒ቺ���邯��ǎ����������オ��킯�ł͂Ȃ��A�����������Ƃł��v�ƌ����Ă��܂����B��̓I�ɐl�����ԂƓ�����̑w���f�[�^�Ŏ������ƁA�Ȃ�قǂ����������Ƃ��A�Ɣ[�����܂����B�`���b�g�����ł����A��x�W�b�N�������Ă݂������̂��Ǝv���Ă�����A�u���Řb�����A����͍s�����Ȃ�܂��Əo�|�����킯�ł��B�e���r�ȏ�ɔ[�����܂����B �@���̕��́A�u���R���{��`�v�Ƃ������t��������ЂƂł��B���S�s�X�n�ɕK�v�Ȃ̂́A�܂��l���Z��ł��邱�ƁA���ɐE�ꂪ���邱�ƁA���ꂩ������{�݂��邢�͕a�@�Ƃ������R�~���j�e�B�[�@�\�����邱�Ƃł���A�Ō�ɏ��Ƃ����邱�Ƃ��Ǝ咣����܂��B�������R�����Ȃ��Ă����ƐH���ƔR������ɓ��葱����d�g�݁A����Έ��S���S�̃l�b�g���[�N��p�ӂ��Ă������Ƃ����咣�ł��B�������A���R���{��`�́A�}�l�[���{��`�̔ے�ł͌����ĂȂ��A�s������c�ɕ�炵�̂ق��������Ƃ����P���Șb�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��āA���{�Љ������n��̉ߑa���A���q���Ƌ}���ȍ���Ƃ���������������\�����߂Ă���̂����R���Əq�ׂĂ��܂��B�u���ʂɐ^�ʖڂō��C�̂���l���A����Ȃ��琶���Ă�����Љ�A���R�ɂ͂���B���R�̕�炵���͐��E�ɒʗp�����v�ƌ����܂��B �@���J����̌����Ƃ���ł́A�u�G�l���M�[���i���オ��n�߂��̂�1995�A96�N�B���{�̐��Y�N��l��������n�߂��̂����傤�Ǔ�������ŁA����炪�d�Ȃ������Ƃɂ��A���{��Ƃ̓G�l���M�[���i�㏸�����i���i�ɂ͓]�ł����A�c��̐��オ����ŘJ���s�ꂩ��ޏo����̂ɍ��킹�āA�l����̑��z�����炷�Ƃ��������Œ��������v�̂������ł��B |
|

| �@���J���킭�A�u���{�l�̑����������Ă��邱�Ƃ́A�l�A�\�N�O�̃C���[�W�Ɋ�Ă����v�̂������ł��B�s���Y�������Ă���Έ��S�Ƃ��܂��ɑ����̐l���v���Ă���ƌ����܂��B���J����́A���̗�Ƃ��Ē��O�ɃN�C�Y���o���܂����B�u�l�A�\�N�O�Ɣ�ׂĎ��E�������Ă���Ǝv���܂����v�E�E�E�u�����Ă���v�Ƃ����l�������ł����B�u�l�A�\�N�O�Ɣ�ׂĎE�l���Ȃ킿���E�������Ă���Ǝv���܂����v�E�E�E�u�����Ă���v�Ƃ����l�������ł����B�u�Ƃ������Ă���̂͒n���ł����A��s�s�ł����v�E�E�E�u�n���ł��v�Ƃ����l�������ł����B�u�V�l�������Ă���̂͒n���ł����A��s�s�ł����v�E�E�E�u�n���ł��v�Ƃ����l�������ł����B�u�Ⴂ�܂��A���ׂċt�ł��v�Ƃ����̂������ł����B �@���J����́A���E�҂������Ă���A���E�̌����������Ă���Ƃ������Ƃ��f�[�^�Ŏ�����܂����B���{�������Ɉ��S�ȍ����Ƃ������ƂJ����͎w�E���܂����B���J�����������ɂ́A���\�Έȏ�̐l�͋�\�܂Ő�����ƌ����܂��B�L���J�[�v�t�@���ł��鑔�J����́A�싅�ɂȂ��炦�āu�l���͂X�܂ł����v�A�ƌ����̂ł��B�X���Ȃ킿90�܂Ő�����ƍl���Đl���v���Ȃ����Ƃ̂��ƁB2010�N����2015�N��5�N�Ԃœ����̐l����36���l�����āA����34���l�͎�ҁA�S�������҂������Ɉړ����Ă��铝�v���o�Ă��܂��B�l���������Ă���͓̂����ȊO�ł͐_�ސ�A���m�A��ʁA����A�������ł��B����œ��{��64�Έȉ��������Ă��Ȃ��͉̂��ꌧ�����A65�Έȏ�̐l�������{��͓����A�Ƃ������̂͑�s�s���ł��B���ꂩ���s�s���͘V�l�䗦�������āA��ÁA���̖��ɒ��ʂ���A���Ɍ������Ȃ�͓̂������Ƃ����̂ł��B�������l�����瓌���͕�炵�₷���X�ł͂Ȃ��Ȃ邻���ł��B |
�y�ʐ^��z�X�e�b�L�����ču������鑔�J�_� �l���͂X�i90�j�܂ł���I �\��5���݁A���l���Ă���65�܂œ����Ƃ��āA�����Ă��鎞�Ԃ̍��v�Ɨ]�Ɏ��Ԃ̍��v�͂��̊ԋ���10�����ԁA�ސE��̗L���������Ԃ�10�����ԁA�����������牄������L�蓾��ƍl���Ă����Ȃ���Ȃ�܂��� |
| �@�u���̍Ō�ɑ��J����́A���{�S����щ���Ă��邯��ǁA�D���ȂƂ���͐����ƎR�`�����Ƃ������Ⴂ�܂����B���y�A�l�Ԑ��A�H�ו��A���낢�뗝�R���q�ׂ��܂����B�����s�����̘e�𗬂�钆�Ð�ɂ́A�H�ɍ����k�サ�A�~�ɂ͔��������܂��B���{�S���ǂ��ɂ����ꂾ���̑傫�ȊX�ł��̂悤���Y��Ȑ삪�X���𗬂��s�s�͖����ƌ����܂��B���������ӂ̎R�X����̕������Ŏs���Ɋ��Ȃ́u���{�����S�I�v�ɑI�ꂽ�����������̗N�o�n����ӏ������钿�����X�A�H���͎��ӂ̔_�������ɓ���A���͔��d�A�n�M���d�A���͔��d�A���z�����d�Ȃǂ̃G�l���M�[�����͂����Ղ肠��A���Ȃ킿���J����̌����Ƃ���́u���R�v�̗v�f�������ɑ����Ă���ƌ����̂ł��B�����������\�[�X�����Đl���W�܂�X�Â���A�E����m�ۂ��A�����{�݂��邢�͕a�@�Ƃ������R�~���j�e�B�[�@�\������A���S���S�̃l�b�g���[�N�����߂Ă܂��l���W�܂�ƌ����܂��B�Ȃ�قǁA��Ɨ��������A�Ƃ����O�ɁA�l���W�܂�d�g�݂Â��肪��ȂȂƔ[�����܂����B �@�܂������ɂ͊���w�Ƃ����f���炵����w�����邶��Ȃ��ł����A�Ƃ������Ⴂ�܂����B�H�w�����_�w���������ł͗L�������A�����{��k�Ђł͒Ôg�h�Ўw�������Ă����n�悪��Q�����Ȃ��A������͍ЊQ�����ɑ�w�������Ď��g��ł���Ƃ��낪�f���炵���Ƃ������Ⴂ�܂����B �@��s�s�ɐl���W�܂�Ǝq�ǂ����Y�܂Ȃ��Ȃ�A�ۈ珊�]�X���A���{������Ă���ƌ����܂��B���R�̕�炵�ň��S���S�̃l�b�g���[�N�̒��ɋ���Ύ��R�Ǝq�ǂ����Y�܂��̂������ł��B�ǂ����ŏ��͎q�ǂ����O�l�Y�߂ƌ����������Ƃ����܂������A�����������ł͂Ȃ��悤�ł��B�K���Ɋ撣��Ȃ��Ă�����Ȃ��琶���Ă�����ꏊ���K�v�Ȃ킯�ł��B�m���ɓ����ɂ͎�҂��W�܂��Ă��邯��ǁA�݂�ȕK���Ɋ撣��Ȃ��Ɛ����Ă����Ȃ��\���ɂȂ��Ă��܂��B��������ƁA��������Ƃ��q�ǂ����Y�ނǂ���ł͂Ȃ��Ƃ����l���]���]���A�Ȃ�قǔ[���ł��B �@������Ƒ��J����͐����L���J�߉߂��Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂������A���{�̂��ׂĂ̒n���m���Ă���l���������Ƃł�����A����͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B���J����͒��B���܂�Ȃ̂ŁA��C�푈�ő��R�Ƃ��ꂽ��Â�암�̕��X���猩��Ƒ�����������Ȃ�����ǁA���͋g�c�������E�˂����̂́A1822�N����̌Y�ɏ�����ꂽ�암�˂̑��n���i�{���F���l�ďG�V�i�j�ɑ���Ǖ�̔O����A�H�c�E��ق̌����K�˂邱�Ƃ��ړI�̈�������Ƃ������Ƃ�b����܂����B�܂������ŁA�����ƂȂ�ΐӔC������ĕ����A�암�ˎm�̂������悳�A���J�������L��̐l���D�����Ƃ��������A���̌��_�ɂ���b�Ȃ̂��Ȃ��Ɗ����܂����B |
 ����A�V���A�J���A�R��̊e�� |
 ���V�W����Ɠo�c�^�R�q���� |

 ���Β��̋��y���� |
 ���߂̈��A�͊�茧�����L��U���ǁE�{��F�u�ǒ� |